
Via Vino
No. 19 "Australia"<オーストラリア>

<日時・場所>
2008年8月9日(土)12:00〜15:00 東京「SALT」
参加者:21名
<今日のワイン>
南オーストラリア・白「ジェネレット・リースリング 2007年」
タスマニア・白「テイマー・リッジ・デヴィルズ・コーナー・シャルドネ 2006年」
ヴィクトリア・赤「リトル・レベル・ピノ・ノワール2006年」
南オーストラリア・赤「ウィンズ・クナワラ・カベルネ・シラーズ・メルロー2005年」
<今日のランチ>
前菜:タスマニア産オーシャントラウトのコンフィ
メイン:クィーンズランド産子羊のアシェット
デザート:パッションフルーツのパブロヴァ




1.はじめに
イギリスの植民地としてのオーストラリアの歴史は、アメリカがイギリスから独立したまさにその時から始まったと言えます。18世紀の終わりに英国からの移民がシドニーに到着し、その後19世紀にかけて各地にワイン産業の基礎が作られました。イギリスはアメリカを独立戦争で失ったことを反省し、気候が温暖で風土病も少ない理想的な植民地オーストラリアを手放さないために、圧政ではなく自治権を与えることで極力良好な関係を築き上げようとしました。その結果
オーストラリアは独立戦争を起こすことなくイギリス連邦の一員にとどまっており、いまやオーストラリアのワインは、英国でフランスワインを凌ぐ取り扱いとなっています。
オーストラリアワインの最大の特徴は、その自由度にあります。フランス系に限らず、イタリアやドイツ由来のあらゆる品種が栽培可能で、かつそれをどのようにブレンドしても構いません。またヨーロッパのワインで最も重視されるテロワールへのこだわりもなく、オーストラリア最高級のワイン「ペンフォールド・グランジ」ですら、数ヵ所の離れた畑の葡萄を自由にブレンドして造られています。ヨーロッパのワイン産地が、その伝統と純血を守るために品種や規格を細かく決めているのに対し、そのような歴史的背景に一切縛られる必要のないことが、オーストラリアワインの最大の強みとなっています。
「オーストラリアを知るための55章」の著者越智道雄氏は、「中世のなかった国の希薄さやはなやかさが、私には性に合う」と述べています。新世界であるオーストラリアの地では、対立する国や民族に属する人々も普通
に触れ合うことができる……歴史と伝統を知ることにより、ワインというアルコール飲料が、独特の深味と輝きを見せてくれることは確かだと思うのですが、一方で歴史を背負うが故の言語や宗教の壁が、進歩を妨げ無用な制限を加えてしまうこともありました。品種も畑も様々に選択し組み合わせることのできるオーストラリアワインは、様々な意味でワインの未来の姿を描き出してくれるように思われます。
オーストラリアは世界で6番目に大きい国ですが、国土の大半は砂漠とステップ(半乾燥地帯)に占められており、ワイン生産地は南の海岸沿いの比較的天候の穏やかな地域に限られます。南部のタスマニアやヴィクトリアのジーロング、西オーストラリア最南部などは特に冷涼な気候となっています。土壌も各地でそれぞれの個性を持っていますが、特に南オーストラリアのクナワラのテラ・ロッサは、表土が赤土でその下に石灰岩質土壌があり、高品質な葡萄栽培に適しています。最も生産量
が多いのはシラーズで、これはフランスのシラーと同じものですが、オーストラリアではよりフルーティで甘い風味に仕上がります。
2.白ワインのテイスティング
●新世界の白ワインとは思えない純粋さ……南オーストラリアのリースリングとタスマニアのシャルドネ



南オーストラリアの「ジェネレット・リースリング 2007年」とタスマニアの「テイマー・リッジ・デヴィルズ・コーナー・シャルドネ
2006年」 を用意して頂きました。
南オーストラリア州は、国内生産量の半分を占めるオーストラリア最大のワイン産地。中でもクレア・ヴァレーは南オーストラリア最北の栽培地域で、内陸性気候のため昼夜の気温差が大きく、土壌が粘土質のためコクのあるワインができます。主要生産品種はリースリングで、比較的ボディのある白ワインに仕上がります。
ジェネレットは、1992年設立の新しく小さなワイナリー。リースリング以外にもセミヨンやシラーズ、そしてグルナッシュを使用したユニークなスパークリングワインなどを生産しています。特にリースリングは果
実味があり、花や柑橘などの華やかな香りとフレッシュな味わいが楽しめます。辛口ながらどこかハチミツレモンの様な親しみやすい自然な甘い香りを持っていました。
一方、タスマニア島は、最も冷涼な気候のワイン産地。早い段階で植樹がなされたものの、1960年まで事実上葡萄栽培は行われていなかったとされています。生産量
は国内全体のわずか0.4%に過ぎませんが、高品質のスパークリングワイン、シャルドネ、ピノ・ノワールが造られています。
テイマー・リッジはテイマー川の西岸に位置し、冷涼な気候でシャルドネやピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランやリースリングなども栽培しています。2006年は温暖で乾燥したヴィンテージで、収穫は例年よりもかなり早めに開始となりました。メロンやグレープフルーツ、ピンクの花などの香りがあり、ソフトな舌触りで、酸味と果
実味がせめぎあうような甘酸っぱさがあります。シャルドネならではのどこかナッツのような香ばしさもしっかりと感じられました。ステンレスタンクによる低温発酵を行い、オーク樽は使いません。以前はオーストラリアのシャルドネというと、カリフォルニア以上に樽香の強いワインが多かったのですが、最近では品種の持ち味を極力生かすようになりました。
このシャルドネに合わせるのは、同じくタスマニア産のオーシャントラウトのコンフィ。まさに絶妙の組み合わせとなりました。
3.赤ワインのテイスティング
●「小さな反抗」と名付けられたピノ・ノワールと、クナワラ最古のワイナリーによるバラエタル・ブレンド

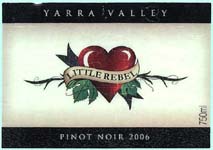

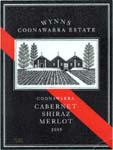
ヴィクトリアの「リトル・レベル・ピノ・ノワール2006年」と、南オーストラリアの「ウィンズ・クナワラ・カベルネ・シラーズ・メルロー2005年」
を用意して頂きました。
ヴィクトリア州は、国内生産量の約20%を占めるワイン産地。19世紀の終わりにフィロキセラに襲われるまで、オーストラリア最大の生産量
を誇っていました。大半の葡萄畑が打ち捨てられた状態にありましたが、1980年代から再び生産量
が増大し、現在では冷涼な海洋性気候に恵まれた高級ワインの生産地へと、見事に復興を遂げています。特にメルボルンの東の郊外にあるヤラ・ヴァレーは、19世紀の黄金期に既に著名なワイン産地となっていましたが、酒精強化ワインが主流を占めていた1920年代から1960年代には、一時期生産が途絶えていました。現在は最高品質のピノ・ノワール産地として知られています。
リトル・レベルは、直訳すると「小さな反抗」。従来の決まり事に左右される事なく自由に楽しむ事をコンセプトに造られています。オーストラリアの中でも冷涼で最高のピノ・ノワールの産地とされるヤラ・ヴァレーで造られた、コストパフォーマンスの高いワインです。コルクの代わりにスクリューキャップを使用しています。ルビー色の透明感のある外観が素晴らしく、ストロベリーの香りが特徴的で、非常にきれいな味わいのピノ・ノワールでした。
一方のウィンズ・ワイナリーは、1896年にスコットランド人ジョン・リドックによって南オーストラリアに設立されたクナワラ最古のワイナリーで、1951年にウィン家の所有となりました。クナワラ最大にして最古の自社畑を守り、著名なテラ・ロッサ土壌による典型的なクナワラスタイルのワインを造っています。フレンチオークとアメリカンオークの新樽・旧樽を組み合わせて熟成させています。カベルネ・ソーヴィニヨン、シラーズ、そしてメルローと自在にブレンドしたこのワインは、チェリー、プラム、そしてミントの風味があり、ジューシーなタンニンとクリーミーなオークの風味が特徴です。濃い色調とまろやかな味わいは、オーストラリア赤ワインの最良の品ならではのものでした。
南オーストラリアでは、ドイツ移民により開発されたバロッサ・ヴァレーと、テラ・ロッサ土壌で知られるクナワラが有名で、前者はシラーズ主体、後者はカベルネ・ソーヴィニヨン主体の生産地となっています。特にクナワラは海洋性気候の影響下にあり、適度に涼しい夏の気候と、広範囲にわたる雲のため、葡萄を充分に完熟させることができます。その結果
、クナワラの赤ワインは、オーストラリアで最もエレガントに仕上がると言われています。
赤ワインに合わせたメイン料理は、クィーンズランド産子羊のアシェット。子羊は当然ながらボルドータイプのワインと相性が良いのですが、こと南半球に関して言えば、ニュージーランドでもオーストラリアでもラムとピノ・ノワールの組み合わせが意外と馴染むようです。
4.オーストラリアワインの歴史
1788年 英国からの移民がシドニーに到着、ハンター・ヴァレーに最初の葡萄園が開設される
1795年 オーストラリア最初のワインができる
1822年 オーストラリアワインが初めて英国へ輸出される
1823年 タスマニアで試験的な葡萄栽培
1827年 英国、オーストラリア全土の領有宣言
1829年 西オーストラリア州に葡萄の苗木がもたらされる
1834年 ヴィクトリア州でワイン生産開始
1837年 南オーストラリア州でワイン生産開始
1847年 バロッサ・ヴァレーでドイツから亡命したシレジア人が入植、ワイン醸造開始
1875年 ヴィクトリア州のジーロングでフィロキセラ発生 以降生産の中心は南オーストラリアへ
1890年 スコットランド人ジョン・リドックがクナワラのペノラを開拓
1899年 ボーア戦争に義勇兵参加
1901年 オーストラリア連邦成立、移住制限法制定〜白豪主義へ
1955〜1960年 酒精強化ワイン全盛期、生産量の9割を占める(現在は5%以下)
1965年 労働党、党綱領から白豪政策を外す
1966年 通貨をドルに移行、英国ポンド経済圏からの離脱
2003年 世界最大輸出市場の英国で、金額ベースで取り扱いがフランスワインを凌ぐ
イギリスはアメリカを独立戦争で失い、その反省からオーストラリアに対しては自治権を認め、緩やかで相互に依存する関係を維持しようとしました。従ってオーストラリアは第2次大戦以後も経済的に英国に大きく依存しており、非白人の移住を制限する白豪主義で知られる国となったのです。英国の地位
が低下しヨーロッパからの移住が減るに従い、世界中から移民を受け入れる他文化主義へと移行したものの、いまだにイギリス連邦に所属し、国家元首は英国女王のエリザベス2世となっています。
大手14社が生産量の73%を占めており、それ故に各社は多くの畑から葡萄を集めて自由にブレンドし、品質の安定した生産を行うことができます。歴史や伝統に左右されない自由度の高さが、オーストラリアワインの強みとなってはいますが、大企業がマーケティングに基づいてワインのブランドを立ち上げているという現状を考えると、市場原理に左右されるという点で逆に大きく制限を受けているのも事実です。
フランスのボルドーやシャンパーニュは、輸出先のイギリスの嗜好に合わせてその味わいを変えてきました。スペインのシェリーやポルトガルのポートも、その販売や生産はイギリスの市場に左右されてきたのです。現在、オーストラリアはフランスを抜いてイギリスの最大ワイン供給国となっていますが、それは一面
においては、世界のワイン市場をリードするイギリスの底力を示しているとも言えるのです。
6.おわりに
オーストラリアワインほど近年劇的に飛躍を遂げたワインはないと言われています。十年間で栽培面
積は8万haから21万haまで拡大し、ワイン流通の中心地イギリスにおいて長年の間主流だったフランスワインを凌ぐ勢いを見せています。
生産の拡大とともに、ワインのスタイルも劇的に変化しています。白の主流は1970年代のセミヨンやリースリングの甘口ワインから、1980年代には辛口の樽を利かせたシャルドネへと変わり、今また品種本来の持ち味を生かしたアロマティックな品種がメインとなりつつあります。2007年の国内消費ではソーヴィニヨン・ブランとセミヨンのブレンドがシャルドネを抜いたと言われ、消費者の嗜好に合わせて次々とスタイルを変えていく自由度の高さが強みとなっているのは確かなようです。
市場原理に左右されがちな新世界ワインですが、しかしこのオーストラリアにおいても、流行にとらわれず、気候と土壌に見合った品種を大切に栽培していこうという動きが、小規模ながら出てきているようです。イタリア系の、栽培が難しいとされるネビオロで造られたオーストラリアワインを試飲する機会があり、そのナチュラルな風味に思わず圧倒された記憶があります。オーストラリアワインについては、現段階においては一言で片付けることは難しく、まだまだこれから思わぬ
方向へ姿形を変えて行くのではないかと思われます。
<今回の1冊>

竹田いさみ「物語オーストラリアの歴史」中公新書
オーストラリアワインは近年急激に変化しているわけですが、その分本屋に並ぶオーストラリアワイン関連の本はやや古いものが多いようなので、今回ご紹介するのはオーストラリア全般
の歴史を扱った一冊。歴史自体はまだ新しいオーストラリアですが、その間、極端な白豪主義から他文化社会へと大きく変化した訳で、それはそのままワインのあり方の変化とも結びついていように思われます。本書ではオーストラリアを、未開拓の分野で次々と研究開発を進めるベンチャー企業になぞらえて、ベンチャー型中企業国家、ミドルパワー外交の国と位
置付け、1970年代にイギリス連邦の一員からイギリス、アメリカ、アジアと連携しつつ独自の道を歩む国へと変貌したと結論付けていますが、現在のオーストラリアワインもまた、その意味でヨーロッパの伝統を踏まえつつ独自性を模索していると言えるのです。