黒い森を抜けて
已岬佳泰
後編
4
喧噪が遠ざかり、ジチは目覚めた。
体中がむず痒く気分はイライラしていた。考えの重心が定まらない。
目を開くと、目の前に不思議そうな顔つきの娘がいた。
「ジチ、どうしたの?」
娘は小さな口をもごもごさせて聞いた。ジチは目をぱちぱちして、娘をまじまじと見た。リナは長細い身体を持っていた。すべすべした体を弓なりにして小さな頭はジチをのぞき込んでいる。くるりと反り返ったヒゲがかわいいし、大きな丸い複眼もきらきら光りとても魅力的だ。
「ねえ、ジチ、変な顔してどうしたの?」
ジチは何も言えずにリナを見ていた。リナは同じ質問を繰り返した。
「なんでもないよ」
言葉はすんなり出てきた。しかし喋りながらも、ジチは興奮を抑えられなかった。切迫感のようなものがジチを追い立てていた。何かをしなければならなかった。何かがなんだか分からなかったけれど、とにかく、何かを見つけて、何かをしなければ、そのイライラは解消できそうになかった。
「なぜ、黒い森なんだ」
ジチは思わず口走っていた。オキたちに言われた黒い森はジチにとって重要な意味を持っている。それは確信に似た思いだった。リナは黒い目をまっすぐジチに向けている。ジチもその目をのぞき込む。リナの目の色にジチの体は反応した。
「オキたちはぼくたちを黒い森へと行かせたいのだ」
ジチはリナのすべすべした外殻に体を巻き付けながら、そう言った。リナは合意した。
「そうかもね。オキたちはここが無くなると警告したけど、それがあたしたちにどう関わり合ってくるかなんて何も言わないし、そのくせあたしにはジチを待てって」
リナは口から長い触覚を伸ばして、ジチの顔を舐めた。
「でも黒い森に行ってどうするんだろう。そこに何かあるんだろうか」
「さあ。それってきっとそこまで行かないとわからない。そんな気がしない?」
そうだろう。きっとそういうものだろう。リナの言葉はリナの甘い触覚と同じように、するりとジチの体に入り込んだ。遠くから蠢動が突き上げてきた。そのままジチは意識を捨てた。リナが何か叫ぶとその体が光りはじめ、ジチの視界は暗くなった。
5
「瞳孔の散大、意識の消失、それに加えて、頭部の損傷が相当にひどい。CTでも脳内の出血が確認されました。本来ならば、すぐに頭を開けて内出血の処置をすべきなんですが、踏み切れないでおります」
「それはどうしてなのですか」
「はい、実は患者、いえ、ご主人の体温が非常に高くて、たぶん脳内の血腫のせいだと思うのですが、脳の中の温度が上がってきているのです。脳細胞や脳神経は大変繊細で熱に大変弱いのです。このままでは、手術をして脳内の出血を止めても、その後遺症の発熱で肝心の脳細胞や神経が死んでしまう怖れが高いと判断しました。そうなると、たとえ回復しても後遺症の心配が大きくなります」
「どういうことでしょうか?」
「例えば、脳細胞が損傷を受けますと、四肢の障害が残ったり、最悪の場合は自意識の戻らない植物人間という怖れもあります」
「ということは、主人に助かる見込みはないと、そういうことでしょうか」
「残念ながら、あまり希望が持てる状況ではありません」
「そんな……」
「今のところ、新しい治療法を使い、なんとか熱を下げるべく努力をしておりますが、九十九パーセント難しいと申し上げざるをえません」
「ああ……」
「この二、三日が勝負だと思います」
「主人には会えないのでしょうか」
「現在、集中治療室ですが、お一人だけでしたら入っていただいても結構ですよ」
「はい、私が入ります。ぜひお願いします」
「では、こちらへどうぞ」
6
きゃっ。
リナの息を飲むような悲鳴で、ジチはあわてて目を開けた。
ふたりはいつの間にか丘に立っており、リナは体をくねらせて丘の向こうを見下ろしていた。
「どうしたというんだ」
ジチは、おそるおそる、リナのとなりに並んで丘の向こうをのぞき込んだ。
「あっ」ジチも、思わずうめいてしまった。
薄い色をした地面は足下ですっぱりと切り落とされたように途絶え、そこは切り立った崖になっていた。その途中に奇妙に折り曲がったモノがいくつも重なって見えた。おびただしい数の死骸だった。死骸はジチとリナの格好によく似ている。それの意味するものをジチは即座に理解した。ジチとリナの前にもここから飛ぼうとしたものがたくさんいたのだ。オキたちがいまだに飛行するものを求めているということは、それらはことごとく墜ちたのだろう。
ジチの体はすくんでしまった。ついには恐ろしさにがたがたと震え始めた。
崖のずっとはるか下の方には黒々とした森が幽かに見えた。鬱蒼とした森はそこから果てしなく地平線の彼方まで続いているようだった。
「あそこまで飛べというのか」
ジチのつぶやきにリナは応えなかった。
「行かなくっちゃ。森に行かなくっちゃ。行かなくっちゃ」
リナが突然つぶやいた。見るとリナの体がぶるぶるとうなり始めていた。それは規則正しいリズムを打っていた。リナは体をくねらせながら、丘の終点つまりは断崖へと身を進めはじめていた。
「ジチ、感じないの? 黒い森が呼んでるよ。ジチ、ついておいで。ついておいで」
リナは歌うように言いながら、丘の終点ですっと立ち上がった。
「待ってくれ」
ジチはとっさにリナの尻尾を踏みつけたが、一瞬早くリナの体は宙に飛び跳ねた。
「ジチーっ、ついておいでーっ」
リナの光る体はくるりくるりと回りながら落ちていき、それでも途中の岩に引っかかることなく、あっという間もなく崖下の黒い森の方へ吸い込まれていった。ジチは呆然と見送った。ジチのまわりには、リナのどきどきする匂いがまだはっきりと漂っていて、リナの遠ざかる声も耳の中に残っていた。
7
「体温は三十三度くらいに冷やして継続して観察中です」
「見通しは?」
「難しそうです。意識も戻りませんし、頭を開けないで様子を見ていますが、瞳孔の収縮が始まりました。左右ともに2ミリです」
「脳温が下がれば瞳孔は収縮する。問題はむしろ脳内出血だな。脳に相当の衝撃があったのだろうから、遅発性出血も調べた方がいいかもしれん」
「遅発性、ですか」
「そうだ、いったんは停まったように見える内出血が突然また再発することがあるんだ。交通事故でその時は大丈夫でも、何日かして突然倒れる例があるだろう。あれは大体これだ」
「はい、CTをもう一回やってみます」
「うむ、患者の家族にはどうした」
「患者の妻に、正直に難しいと伝えました。集中治療室で、変わり果てた患者を見せましたので、覚悟はできたようです」
「そうか、それで例の件は話してくれたか」
「臓器提供の件ですか。いえ、まだです。もう少し様子を見たいと思いまして」
「そうか、まあいい。でもその時が来たら、うちが一番に貰いたいので連絡は頼むよ」
「分かりました」
8
「リナがやっと行ったか」
放心して立ちつくすジチのすぐ後ろに、いつの間にかオキたちが集まってきていた。
「リナは落ちてしまった……」
ジチのつぶやきにオキたちは互いの顔を見合わせる。そして大きく上下に動き始めた。
「ジチも飛ぶ。やがて飛ぶ。飛ばないと何もはじまらん」
オキたちの声はジチの体に直接響いたようだった。ジチの体の奥でなにかがはじけた。頭はくらくらし体がふるえだした。小さな規則的な震えがだんだん大きくなり、体全体が熱くなってくる。震えはいっそうひどくなり、とうとう、つられて首がくねくねと動くまでになった。ジチは抑えきれない衝動に突き動かされて体を大きく反転させ、崖の上に立ち上がった。
黒い森へ行くのだ。
衝動は繰り返し繰り返しジチを突き上げた。オキたちは身を寄せ合うようにしてジチを見守っている様子だ。
「無理なんじゃないか」
ひとりのオキがつぶやく。
「しぃっ。仕方のないことじゃ。そんなこと今さら言っても仕方がないことじゃ。わしらは、ここで待つしかあるまい」
崖の上で一度大きく立ち上がったジチは、何のためらいもなく、次の瞬間には地面を蹴って宙に体を投げ出していた。ジチの体はくるりと回転し、そして震えながら黒い森の方へ落ちていった。ふるえは止まらないまま、体はよじれたまま・・・。
落ちながらも、不思議とジチに恐怖心はなかった。時折、遙か彼方の黒い森を見つめながら、猛スピードで落ちていく。途中で急に背中がかゆくなったかと思うと変な音とともに、背中あたりが軽くなった。ジチはあわてて後ろを見た。体が半分に折れていた。触覚をこすり合わせた。体が軽くなり、気がつくとジチは宙に止まっていた。
「ジチーっ」
リナの声だ。
見ると相変わらず体をきらきら輝かせながら、やはり体を半分に折ったリナがすぐ下を飛んでいた。
「あれを見て、ジチ」
ひとまわりしたリナの指す方には、さっき折れて外れたジチの半身が崖の岩の上に転がっていた。いや、ジチの半身だけではない。あたり一面の岩には、似たような折れた半身がたくさん落ちていたのだ。そうか、そういうことか。
ジチは折れた半身を確認しようと岩の方へ行きかけ、そして思いとどまってリナを見上げた。
「ぼくらは飛べる体に変態したんだ」
ジチはすいすいと飛んでいるリナにやっと追いつくと、今度はふたり並んでさらに大きな輪をかいて飛んだ。たぶん、丘の上のオキたちにも見えたはずだ。ふたりは、しばらくそうして飛んでいたが、やがて、黒々とした森を目指して急降下を始めた。
9
「CTのフィルムをお持ちしました」
「うわっ、いかん。血種が大きくなってきているな。しかも前葉体にかかっている。開頭手術の準備をしてくれ」
「はい、スタンバイします」
「瞳孔は?」
「左4ミリ、右3ミリ、不安定です」
「うーん、いかんいかん。これが遅発性出血かもしれないな。急いでくれ。体温は?」
「33.5度で変化はありません。冷却装置、モニター異常なし」
「よし。ストレッチャーを入れてくれ。頭を開けよう」
10
黒い森は遠かった。ジチとリナは飛びつづけた。しかし、飛んでも飛んでも、ちっとも近づかない黒い森は、依然はるか彼方に霞んでいた。ジチは飛びながら、また胸の中がもやもやしてくるのを感じた。それは、以前にここに来たことがあるという奇妙な既視感だった。なぜだろう。一体自分はどこから来て、どこに向かっているんだろう。ただひたすら、強い衝動だけがジチを駆り立てていた。黒い森へ行くのだ、黒い森へ行く、そして……。
すぐ隣りでリナは笑いながら飛んでいた。
「また難しいことを考えているのね」
リナは図星を突いてきた。
「どうして、ジチはそうやっていちいち考えないと動けないのかしらね。あたしみたいに、やりたいからやるというのじゃ駄目なの?」
ジチは今度こそじゅうぶんに考えようと思った。目が覚めてからずっと体に貼り付いていた違和感はいまだにそこにある。既視感もジチを悩ませる。
ジチはもどかしかった。
何かが見えているようで、実は何も分かっていなかった。めざすところは黒い森なのだ。そう教えられ、目指して飛んでいる。飛び続けることには満足と安堵がある。でも、それがどういうことなのか。もういっぽうで自問するものがあるのだ。
「ねえ。黒い森っていったい何だろう」
その黒さは遠目にもそう見える。でも、本当にそうなのか。「黒い」森と言われたから、黒いだけなのではないか。現にこんなに精一杯のスピードで飛んでいるのに、ちっとも近づかないではないか。
その時ふと、ジチの頭をある考えが通り過ぎた。それは、すぐに振り払いたい嫌な考えだった。
このまま、自分は黒い森を目指して飛びつづける。ひたすら飛びつづける。黒い森が見えている限り、ひたすら、ひたすら……。疲れ墜ちる時まで飛び続けるのだ。
11
竹中章一は陽の光を感じた。のどが渇いていた。焦点は定まらない。誰かが声をかけていた。ゆっくりと首を動かす。陽の光と思ったのは部屋の照明のようだった。頭がいくつも揺れている。ぼんやりと並んだ人達の顔が目にはいる。
「黒い森に着いたかな」
それが竹中が七日ぶりに意識を取り戻して、初めて口にした言葉だった。
(了)
参考文献:柳田邦男「脳治療革命」(文藝春秋社)
○×評価をお願いします
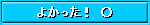
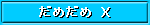
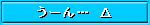
|